皆さん、こんにちは。
管理人のまっしーです。
新型コロナウイルスの影響で吹奏楽の活動に制約を受けている方も多いことと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は、樽屋雅徳作曲の『民衆を導く自由の女神』をご紹介します。

樽屋さんの曲をご紹介するのはこれで4曲目になるけど、樽屋さんの曲ってどれもタイトルが独特で面白いよね
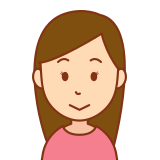
そうね。『民衆を導く自由の女神』って、ドラクロワの絵画よね。パリのルーヴル美術館に収蔵されているわね
はい。そうなんです。冒頭の写真がその絵画です。
実は、この冒頭の写真は、まっしーがパリのルーヴル美術館に行って撮影してきたものです(新型コロナが発生する前にフランスに行ってきました)。
この絵画はとても大きくて、高さ2.6m x 横3.3mもあります。その大きさが分かるように、鑑賞している人も一緒に写真に収めてみました。

普通の家だと、床から天井までに収まりきらないくらいの高さだよね
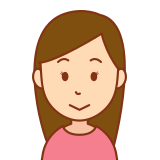
ところで、この絵画と曲はどう関係しているのかしら?
はい、では早速、曲についてご紹介してきましょう!
『民衆を導く自由の女神』とは?
絵画はドラクロワの傑作
この絵画は、フランスの画家、ウジェーヌ・ドラクロワによって1830年に描かれたもので、現在、パリのルーヴル美術館に収蔵されています。
「女神」とは誰なのか
この絵画の原題である『仏:La Liberté guidant le peuple』(英:Liberty Leading the People)は、直訳すると「民衆を導く自由」となります。つまり、「女神」という表現はどこにも見当たらないのです。
実は、《民衆を導く自由の女神》の「女神」という表現は、日本で慣習的に付けられているものなのです。
「自由の女神」という表現は日本では広く浸透しているので、ちょっと意外な気もしますよね。
それでは、この「女神」とは、一体誰で、どのような人物なのでしょうか?
自由の女神「マリアンヌ」
この絵画の中心には、フランス国旗を掲げて民衆を導く女性が描かれています。この女性は「マリアンヌ」と呼ばれ、「フランスを象徴する女性」、あるいは「フランスを擬人化したイメージ」とされています。
つまり、この自由の女神「マリアンヌ」は、ドラクロワがフランスを比喩的に表現したものなのです。

実在の歴史上の人物をモデルにしたわけではないんだね
舞台はフランス7月革命のパリ
この絵画は、19世紀に起きたフランス7月革命のパリが舞台となっています。
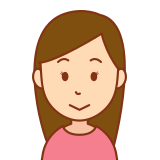
「フランス7月革命」は、18世紀に起きた「フランス革命」とは異なるのよね
はい。ちょっと紛らわしいですよね。せっかくなので、簡単に解説しておきましょう。
フランス7月革命とは
フランス7月革命とは、1830年7月27日から29日にかけてフランスで起こった市民革命で、フランスでは「栄光の三日間」とも言われています。
民衆が三色旗を掲げて立ち上がる
フランス革命(1789-1799年)の後、1815年の王政復古によって王位に就いたルイ18世、そしてその後を継いだ弟シャルル10世はフランス革命の成果を無視して反動的な政治を行ったため、市民階級の間で不満が高まっていました。
シャルル10世は、言論弾圧や旧貴族保護などを進めたことに加え、議会の強制的な解散や選挙権の大幅縮小などを強行したことから、1830年7月、学生・労働者を中心にしたパリの民衆は三色旗を掲げて蜂起し、テュイルリー宮殿、ルーヴル宮殿を次々と占拠していったのです。
民衆の勝利とシャルル10世の退位
ついに同年7月31日、民衆の支持を受けたオルレアン公ルイ・フィリップが市庁舎のバルコニーに姿を現し、民衆に歓呼の声で迎えられました。
8月2日、国王シャルル10世は退位し、処刑を恐れてオーストリアに亡命します。後継政府には「国民王」ルイ・フィリップが立ち、ここにフランスは立憲君主制に移行するのです。

なるほど、フランス7月革命の背景が分かってきたよ
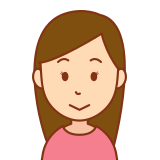
自由の女神「マリアンヌ」は、フランスを象徴的に表したものだということも分かったわ
樽屋雅徳作曲『民衆を導く自由の女神』
さて、ようやく本題の吹奏楽曲、樽屋雅徳作曲の『民衆を導く自由の女神』に入ります。
この曲は、曲名からも分かるとおり、やはりドラクロワの絵画をモチーフに作られています。
絵画と同様、この曲も革命の展開に沿って作曲されています。
冒頭は、木管楽器が静かに奏で始め、これから始まるであろう嵐(革命)の前の静けさを感じさせます。
続いて、重々しく金管楽器が登場します。武器を手にする民衆を力強く表現しているようです。
さらに続く木管楽器とトランペットのテーマは、民衆を導く女神「マリアンヌ」の神々しさを鮮やかに印象づけます。
民衆の蜂起が起き、暴動が革命へと展開する場面では、クラリネットのテーマが喧噪のごとく鳴り響き、それをフルート・ピッコロが受け継ぐ形で盛り上げ、革命の激しさが増していく様子を表現していきます。
やがて暴動が収まると、再び女神マリアンヌが登場します。ユーフォニアムの柔らかくあたたかいソロです。
そしてこの美しいソロは高音木管楽器、オーボエ、ホルン、トランペット、チューバへと受け継がれていきます。こうして女神のテーマは繰り返し奏でられ、壮大なエンディングを迎えます。

樽屋作品の魅力である「物語性のある音楽」が遺憾なく発揮されているよね
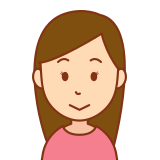
そうよね。壮大でかっこいい中に美しさがあるのも魅了よね
演奏音源のご紹介
ここで、『民衆を導く自由の女神』のおすすめの演奏音源をご紹介します。
実は、この曲は、YouTubeで公開されている音源が比較的少ないのです。このため、今回は1つだけに限ってご紹介します。
航空自衛隊西部音楽隊による演奏です。
なお、上でご紹介したユーフォニアムの美しいソロは、以下の動画の4分58秒頃~です。
コンクールでの演奏実績は?
さて次に、吹奏楽コンクールでの演奏実績についてもご紹介しておきます。
ここでは、県大会における演奏実績にスポットを当てることとします。
2004年に30団体が初めてコンクールで演奏し、2005年に55団体が演奏したのをピークに、その後は徐々に減少傾向にありますが、長く人気を維持していると言えます(数字は、小/中/高/大/職場一般部門の合計です)。
どちらかというと中学校での採用が多い傾向にありますが、高校など他の部門でも演奏されています。
⇒吹奏楽コンクールデータベース「Musica Bella」へのリンク(外部リンク)
編成と難易度(グレード)
編成と難易度は以下のとおりです。
<編成>
Picc.(Fl持替) / Fl.1-2 / Ob.(※) / Bsn.(※) / Eb Cl.(※) / Bb Cl.1-3 / B.Cl. / A.Sax.1-2 / T.Sax. / B.Sax. / Trp.1-3 / Hrn.1-4 / Trb.1-3 / Euph. / Tuba / St.Bass / Timp. / C.Cym. / S.Cym. / B.D. / 4Toms / Chime / Glock. / Marimba(※) / Harp(※) / Piano
(※)はOption
<グレード(難易度)>
4(あくまでも目安です)
<演奏時間>
約7分30秒
参考文献:CAFUAレコードHP
楽譜の入手方法
『民衆を導く自由の女神』の吹奏楽版の楽譜は、レンタル譜となっています(残念ながら購入はできません)。
楽譜のレンタルは、出版社のホームページから申し込み可能です。
最後に
いかがでしたか?
今回は『民衆を導く自由の女神』について、絵画と吹奏楽曲の両面からご紹介してみました。
いつも思うのですが、樽屋さんの曲って、どれも壮大でかっこよくて、それでいて美しいソロやメロディがさりげなく散りばめられていて、魅力的ですよね。

この曲って、エンディングの盛り上がり方とかが最高にかっこいいよね
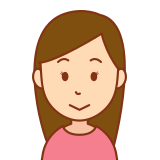
ねえ、まっしー、また樽屋さんの曲を紹介しましょうよ
そうですね。また今後にご期待ください。次はどの曲にしようかな・・・
もしよかったら、Twitterで遠慮なくリクエストくださいね。
また、宜しければ、これまでにご紹介した樽屋さんの他の曲の記事もぜひご覧ください。
では、また次回の記事でお会いしましょう!
次回の記事は、ロバート・ジェイガー作曲『シンフォニア・ノビリッシマ』です。お楽しみに!






