皆さん、こんにちは。管理人のまっしーです。
今回は2021年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅴ『吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃』について、曲にまつわる情報や演奏動画等をご紹介していきます。

課題曲のご紹介も、いよいよ5曲目だね
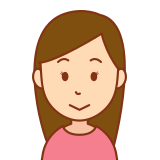
今回も、Webで公開されている課題曲の演奏をご紹介していきますね
当サイトでは、さまざまな吹奏楽団の「課題曲の演奏動画」をご紹介することで、コンクールに挑戦する皆さんのお役に立ちたいと考えています。

記事の最後に課題曲Ⅰ~Ⅳの記事へのリンクも掲載しているので、ぜひチェックしてね
では早速、『吹奏楽のための「幻想曲」』の概要からご説明していきます。
吹奏楽のための「幻想曲」ってどんな曲?
作曲者について
『吹奏楽のための「幻想曲」』の作曲者である尾方凛斗(おがた・りんと)氏は、1995年徳島市出身で、日本大学芸術学部を卒業後、2020年3月時点では、東京音楽大学大学院作曲指揮専攻作曲研究領域に在籍されています。

大学院に在籍されている若い作曲家さんなんだね
本作品は、第12回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位に輝いた楽曲で、2020年度の課題曲Ⅴに選定されています。
曲の概要について
課題曲Ⅴということで、Ⅰ~Ⅳと比較するとやはり難解な印象があります。
作曲者の尾方凛斗氏は、この曲について次のように述べられています。
この作品では、作品の主要な素材として、アルノルト・シェーンベルクが晩年に残した《ヴァイオリンのためのピアノ伴奏付き幻想曲》で用いられている十二音技法に基づく音列を引用している。その音列を私なりの方法で運用した、繊細で流動的なテクスチュアを特徴とする前半部と、力強い律動を含有する行進曲の様式に音列が搭載される後半部の2部で構成されている。繊細な前半部と、重厚な後半部。この相反する筆致を通して、吹奏楽による幻想的な音空間の創出を目指したものである。
全日本吹奏楽連盟会報「すいそうがく」 2019.12 No.212

説明を聞くだけでも難しい感じがするよね
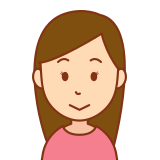
そうね。シェーンベルクが用いた「十二音技法」とはどういうものなのかしら?
「十二音技法」とは何か?
十二音技法とは、シェーンベルクが体系化したとされる演奏技法で、オクターブ内の12の音を均等に用いることにより調性を持たせないようにする作曲技法です。
このため、十二音技法により作られた音楽には一般に調性がなく、「無調の音楽」とも言われています。
文字で読むと難しいですが、記事の後半でご紹介する演奏動画をご覧になると「無調の音楽」を実感いただけるものと思います。
管楽器奏者に特殊奏法が求められる?
この曲では、主に管楽器奏者に対して、いくつかの特殊な奏法が指示されています。
例として、実際に楽譜に記載されている面白い(?)指示を2つご紹介しておきます。
- 【Tb・Euph・Tubaへの指示】:breath sounds (through the instrument)
⇒逆さに持ったマウスピースをマウスパイプの入り口に当てて、息(子音[s]を発しながら)を吹き込む。EuphoniumとTubaはハーフバルブで演奏する。マウスピースを着脱する際には、不意の金属音等に注意を払うこと。 - 【Tp・Hrへの指示】:breath sounds (ため息ha) (voiceless) without instrument

楽譜に実際に上記のとおり記載されているんだね。驚いたよ
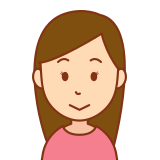
この後の演奏動画②で「特殊奏法」をご紹介するのでご覧くださいね
『吹奏楽のための「幻想曲」』の編成
編成は以下のとおりです。
オーボエとファゴットが2管編成となっていたり、ホルンに4thがあるなど、5つの課題曲の中では最も大きな編成となっています。
Picc. / Fl.1-2 / Ob.1-2 / Bsn.1-2 / Eb Cl. / Cl.1-3 / A.Cl. / B.Cl. / A.Sax.1-2 / T.Sax. / B.Sax. / Trp.1-3 / Hrn.1-4 / Trb.1-3 / Euph. / Tuba / St.Bass / Timp. / Perc.1( Vibra., S.D.) / Perc.2(S.Cym., Sizzle Cym., Glock., Whip) / Perc.3(Maracas, B.D., Ratchet) / Perc.4(Large Gong, Tublarbells, Tri., S.Cym.) / Police Whistle

ちなみに、演奏時間は約3分半と短めだよ
演奏動画
それでは、演奏動画を2つご紹介します。
なお、複数の演奏動画をご紹介しますが、当サイトは演奏の批評・批判を行うことは目的としておりませんので、その点をご理解いただいた上でご覧いただければと思います。
①北海道教育大学函館校吹奏楽団
最初にご紹介するのは、北海道教育大学函館校吹奏楽団さんによる演奏です。
2020年2月中旬に全国に先駆けていち早くWebで公開された演奏動画です。
課題曲Ⅴのような難解な曲を短期間にここまで仕上げられるというのは、さすが全国大会の常連さんだと思います。
②WISH Wind Orchestra
次に、プロによる演奏です。
もはや吹奏楽経験者の方にはご説明不要だと思いますが、当サイトでお馴染みの「WISH Wind Orchestra」による演奏です。
ちなみに、前段でご紹介した「特殊奏法」は、2:10~2:16頃のあたりです(その他にも随所にあります)。

奥深くて面白い曲だよね。特殊奏法も分かったよ
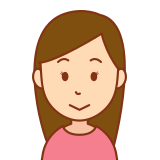
十二音技法の無調性でカオスな感じもよく分かったわ
CDのご紹介
ここで、東京佼成ウインドオーケストラによる注目のLIVE録音のCDをご紹介します!
やはり、伝統ある名門プロ吹奏楽団による課題曲演奏は気になりますよね。ちなみに、このCDは、Amazon限定商品です。ぜひお見逃しなく。
最後に
いかがでしたか?
やはり、課題曲Ⅴは、Ⅰ~Ⅳと比べると音楽面でも技術面でも大きく異なりますね。
シェーンベルクの「十二音技法」は難しいように思えますが、理屈を知った上で聴いてみると、単なる難解な音楽ではなく面白さが分かるような気がします。
コンクールで課題曲Ⅴを演奏される高校生以上の皆さん、ぜひ十二音技法に悩まされながら(笑)楽しんで演奏なさってください。
もし宜しければ、課題曲Ⅰ~Ⅳの記事もご覧ください。
では、また次の記事でお会いしましょう!







