こんにちは。管理人のまっしーです。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
当サイトでは、吹奏楽の名曲・名演を、おすすめの演奏動画とともにご紹介しています。
中でも今回は、吹奏楽で特に演奏したいと思う人気の「かっこいい曲」を20曲厳選してご紹介します。
吹奏楽コンクールや定期演奏会などの各種コンサートでは、やはり「かっこいい曲」を演奏するとインパクトがありますよね。

吹奏楽をやっている人なら、やっぱりかっこいい曲を演奏したいよね
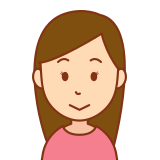
そうね。でも、どんな「かっこいい曲」があるのかしら?
「カッコいい曲」って、どんな曲?
ところで、「かっこいい曲」と言っても、いろんな意味での「かっこいい曲」があると思うんです。
例えば、金管奏者なら「金管楽器がかっこいい」とか、サックス奏者なら「サックスソロがかっこいい」とか、打楽器奏者なら「ドラムがかっこいい」等々、、人によってイメージも異なりますよね。
また、ひと言で「吹奏楽の曲」といっても、クラシックからの編曲版もあれば、ポップスアレンジ曲や、吹奏楽オリジナル曲など、ジャンルも様々です。
そこで、今回は、ジャンル別に、また、できるだけ多くの楽器・パートにスポットが当たるように、「かっこいい曲」をあれこれご紹介していこうと思います。
選曲の基準は?
今回の選曲基準は、ずばり「管理人がかっこいいと思う曲」です。

えっ? まっしーの好みが基準なの?
はい。これまでの記事では、事前にTwitterでアンケートを募ったり、周囲の吹奏楽関係者に意見を聞いたりしていましたが、今回は完全に管理人の独断と偏見による「わがまま企画」となっております。
ただし、独りよがりにならないよう、なるべくよく知られた有名曲から選びます。
では、早速始めましょう。
かっこいい曲【クラシック】
初めに、クラシック曲から4曲ご紹介します。
①『祝典序曲』(ショスタコーヴィチ)
『祝典序曲』は、D.ショスタコーヴィチによって1947年に作曲されたオーケストラ曲です。
冒頭は、トランペットの華やかなファンファーレで始まります。
冒頭のファンファーレだけでも十分かっこいいのですが、実は後半にもう一度このファンファーレが形を変えて登場します。
その後半のファンファーレは、トランペットだけでなくその他の金管楽器、木管楽器、打楽器、そして、バンダ(banda:舞台外での演奏者)も加わって、さらに壮大な音楽となります。
今回ご紹介する龍谷大学吹奏楽部の演奏動画↓では、近畿大学吹奏楽部の皆さんがバンダとして賛助で登場しています(5:13頃~)。このバンダが登場する部分から最後にかけては、一層迫力が増してカッコいいです!
<演奏①:龍谷大学吹奏楽部(2015年)>今回ご紹介する演奏動画について
実は、このあと記事をご覧いただくとお分かりいただけるのですが、今回ご紹介する20曲の演奏動画のうち約半数(8曲)が龍谷大学吹奏楽部さんの演奏動画となっています。
これは、Webで公開されている名演を探していると、どうしてもレベルの高い演奏をされる龍谷大学吹奏楽部の演奏に行き着くためです。特に恣意性はありませんのでご了承ください。

龍谷大学吹奏楽部の皆さん、いつもありがとうございます!
②序曲『1812年』(チャイコフスキー)
序曲『1812年』は、P.I.チャイコフスキーによって1880年に作曲されたオーケストラ曲です。タイトルの「1812年」とは、ナポレオン軍がロシアに遠征した年を指しています。
吹奏楽版の冒頭は、サックス・アンサンブルで静かに始まります。
この静かなサックス・アンサンブルも1つのかっこ良さの形ではありますが、この曲は、やはりクライマックスとなる後半が最大の見せ場です。
ストーリーで言えば、ナポレオン率いるフランス軍がロシア軍に敗れてモスクワの教会の鐘が鳴り響き、祝砲とともにロシア帝国国歌が流れる場面です。
具体的には、チャイム(鐘)が鳴り響き、バンダが登場し、大砲が鳴る場面です(12:33頃~)。
実は、楽譜上、「大砲(cannon)」の指定があるのですが、通常はバスドラムで代用される場合が多く、以下の動画では5台ものバスドラムが使用されています。
今回ご紹介する演奏動画は、再び龍谷大学吹奏楽部によるものです。さすが全国レベルの演奏で、最後の最後までかっこいいです!
<演奏②:龍谷大学吹奏楽部(2010年)>ちなみに、ご参考までに、本物の「大砲」を使用して演奏すると、こうなります↓。
③組曲『惑星』より「木星」(ホルスト)
組曲『惑星』の「木星」は、ホルストによって100年以上も前に作曲されたオーケストラの名曲です。1世紀も昔に作られた曲とは思えないほど、今でも斬新で神秘さが感じられる曲です。
冒頭からホルンとトランペットが活躍してかっこいいのですが、意外と知られていないのが2セットものティンパニを使用する点です。
ティンパニを2セットも並べて演奏する様子は視覚的にも音響的にもかっこいいので、特にパーカッションの皆さんは注目です!
<演奏③:近畿大学吹奏楽部(2011年)>④『カルミナ・ブラーナ』(オルフ)
『カルミナ・ブラーナ』は、カール・オルフによって1936年に作曲された、オーケストラと合唱、ソプラノ・アルト・テノールの独唱、バレエのための舞台音楽です。
『カルミナ・ブラーナ』の魅力は、なんと言ってもその壮大なスケールの音楽にあると言えます。
原曲(オーケストラ版)は、全24曲の小曲から構成された約1時間の曲です。
今回ご紹介する龍谷大学吹奏楽部の演奏は、吹奏楽用に13曲を抜粋して編曲されたもの(ジョン・クランス編曲版)ですが、それでも約27分あります。
第1曲目の『おお、運命の女神よ』は、おそらく誰もが一度は耳にしたことのある有名な曲です。
実は、この第1曲は、最終曲として最後にもう一度登場します(25:03頃~)。この再び登場する瞬間がとてもカッコいいのです。
なお、この曲は、さらに抜粋して吹奏楽コンクールで演奏されることもあり、自由曲としてもおすすめです【グレード5】。
<演奏④:龍谷大学吹奏楽部(2017年)>かっこいい曲【吹奏楽曲】
次に、吹奏楽オリジナル曲(英国式ブラスバンド曲を含みます)から7曲ご紹介します。
⑤『ブリュッセル・レクイエム』
『ブリュッセル・レクイエム』は、ベルト・アッペルモントによって2016年に作曲された英国式ブラスバンド曲です。吹奏楽版は、後に作曲者本人によって編曲されたものです。
テロの犠牲者へのレクイエムを「かっこいい」と評するのは適切ではないかもしれません。
しかし、この、ときにレクイエムらしからぬ一面も感じられる「派手な」レクイエムは、多くの吹奏楽団から広く支持されています。実際、2019年の吹奏楽コンクールでは、この曲が全国的に大ブームとなりました。
個人的には、よりインパクトのある演奏という意味では、原曲の英国式ブラスバンド版の方を聴くことをおすすめします。
非常に高速なパッセージを金管楽器(と打楽器)だけで演奏されていて圧倒されます。このため、今回は敢えて英国式ブラスバンド版の方をご紹介します。
ちなみに、以前、「吹奏楽版」と「英国式ブラスバンド版」の人気投票を行ったところ、両者ほぼ互角の人気でした。
<演奏⑤:Festival Brass Band>なお、吹奏楽版と聴き比べてみたい方は、ぜひ「関連記事」をご覧ください【グレード6】。
ここからは、クロード・トーマス・スミス(C.T.スミス)の3大難曲を3曲続けてご紹介します。C.T.スミスの曲は、端的に言うと「超絶に難しくて超絶にかっこいい曲」が多く、非常に人気が高いです。
⑥『フェスティヴァル・ヴァリエーション』
『フェスティヴァル・ヴァリエーション』は、1982年に作曲されたC.T.スミスの代表作で、スミスによる吹奏楽曲の中でも最高傑作の1つと言われています。
この曲を発表するや否や大反響を呼び、日本においても一大センセーションが起きました。
「スミスによるホルン奏者への嫌がらせ」と語られるくらいホルンにとっては難曲ですが、それはホルンのカッコよさの裏返しでもあります。
演奏は、NHK交響楽団のウインド・セクションです。さすがN響メンバーだけあって文句なしに上手いし、演奏に余裕があって簡単そうにも聴こえてくるから不思議です。【グレード6】
<演奏⑥:N響ウィンドセクション>⑦『華麗なる舞曲』
『華麗なる舞曲』は、1986年にC.T.スミスによって作曲された曲で、スミス作品の中でも最も難しい曲とも言われている名曲です。
最初の数小節を聴いただけでも、いかに難しい曲であるかがよく分かります。
ホルンが難しいのはもはや「お約束」としても、ピッコロトランペットを始めとした難易度の高いソロの連続や、一糸乱れぬ木管楽器の高速パッセージなど、いずれのパートも超絶に高度な技術と演奏力が求められます。
以下にご紹介するのは、海上自衛隊東京音楽隊の皆さんによる演奏です。
文字通り華麗なる見事な演奏です【グレード6】
<演奏⑦:海上自衛隊東京音楽隊>⑧『ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲』
『ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲』もまた、C.T.スミスによって作曲された超難曲で人気の名曲です。
曲名に「讃美歌」とあるように、曲中に美しいコラールも登場するのですが、そこはやはりスミス作品で、冒頭は難易度の高いハイトーンと高速パッセージから始まります。
この曲は、上でご紹介したスミスの2曲と比べると、華やかさは比較的控えめです。
ただ、その分、静かな部分と華やかな部分のコントラストが際立っていて印象的です。トランペットを始めとした難易度の高いソロが活躍し、他の2曲とは異なるカッコよさのある名曲だと思います。【グレード6】
<演奏⑧:龍谷大学吹奏楽部(2018年度)>上記4曲(⑤~⑧)は【グレード6】と最高難度の曲でしたが、次に【グレード5】以下の曲を3曲ご紹介します(⑨~⑪)。
⑨『ジュビリー序曲』
『ジュビリー序曲』は、フィリップ・スパークによって作曲された人気作品です。
原曲は英国式ブラスバンドのための曲でしたが、とても好評であったため、スパーク自身によって吹奏楽版に編曲されました。
冒頭は、華やかなファンファーレで始まります。
原曲が英国式ブラスバンド版ということもあり、吹奏楽版でも金管楽器がとても華やかでかっこいいです。
スパークの作品には、このほか、『宇宙の音楽』(グレード6)や、『ドラゴンの年』(グレード5)など、特に金管楽器がきらきらと輝くように活躍する曲が多いので、こうしたブラスバンド的なカッコよさを求める方には特にスパーク作品をおすすめします。【グレード5】
<演奏⑨:WISH Wind Orchestra>⑩『エル・カミーノ・レアル』
『エル・カミーノ・レアル』は、アルフレッド・リード作品の中でも特に人気のある曲の1つです。
冒頭から「スペイン」を想起させるカスタネットのリズムの前奏で始まり、そのあとホルンの活躍するメロディが続きます。
また、この曲は、A.リード特有のコード進行、すなわち、長調と短調が短い間隔で交互に現れる、明-暗-明-暗の反転模様が印象的でかっこいいです。
今回ご紹介する演奏はN響のウインドセクションによるもので、さすがN響メンバーと思える演奏です。【グレード5】
<演奏⑩:NHK交響楽団ウインドセクション>⑪『マードックからの最後の手紙』
『マードックからの最後の手紙』は、樽屋雅徳作品を代表する人気曲です(通常版/特別版/小編成版あり)。
この曲は、豪華客船「タイタニック号」の一等航海士であるマードックと、タイタニック号の沈没事故を題材に作曲されています。
まるで映画『タイタニック』を観ているような臨場感が感じられる音楽で、上でご紹介した【グレード5~6】の作品のような派手さはないものの、樽屋作品らしい独特の雰囲気と魅力のある曲です。【グレード3+~4】
今回ご紹介するのは「原典版」ですが、この曲には「原典版」「特別版」「小編成版」「2021年版」の4種類の楽譜があります。それぞれの違いなどについては以下でご紹介する詳細記事をご参照ください。
<演奏⑪:龍谷大学吹奏楽部(2012年)>かっこいい曲【行進曲・マーチ】
⑫『星条旗よ永遠なれ』《Jazz編曲》 ~SOUSA’S HOLIDAY~
原曲は、スーザ作曲のマーチ『星条旗よ永遠なれ』ですが、これを真島俊夫さんがJazz風にアレンジされたのが『SOUSA’S HOLIDAY』です。真島俊夫さんは、『宝島』や『オーメンズ・オブ・ラブ』の吹奏楽版を編曲された方、といえばほとんどの方はお分かりでしょう。
原曲のマーチをそのまま演奏するのも良いのですが、このJazz編曲版は、ドラムセットも加わっていて、Jazzのリズムとメロディーがお洒落でかっこいいです。それに、以下の動画でご紹介する川口市立青木中学校の演奏が大人顔負けの演奏で、聴いていて実に楽しいです。
とても盛り上がる曲なので、アンコール曲としてもおすすめです。
<演奏⑫:川口市立青木中学校吹奏楽部>⑬コンサートマーチ『アルセナール』
『アルセナール』は、ヤン・ヴァンデルロースト作曲のコンサート・マーチです。
格調高い音楽が特徴のマーチなので、コンサートや式典での演奏曲としても人気の曲です。
今回ご紹介する動画の指揮者は、作曲者ご本人です。曲自体もかっこいいのですが、作曲者自身による指揮の姿もかっこよく、注目です。
<演奏⑬:尚美ウインドオーケストラ>⑭行進曲『威風堂々』第1番
『威風堂々』は、エドワード・エルガー作曲の人気曲の1つです。
特に第1番は、英国の第二の国歌とも言われるほど愛されている名曲で、派手さや華やかさは少ないものの、伝統や格式、そして威厳や重厚さが感じられ、他のマーチとはまた違ったかっこ良さがあります。
<演奏⑭:龍谷大学吹奏楽部(2007年)>かっこいい曲【コンクール課題曲】
⑮『高度な技術への指標』
『高度な技術への指標』(河辺公一 作曲)は、1974年の吹奏楽コンクール課題曲です。
コンクール課題曲として初めてドラムセットが取り入れられた、最初のポップス課題曲で、後にご紹介する『ディスコ・キッド』などのドラムセット入りポップス課題曲の先駆けともなった人気曲です。
曲名のとおり、非常に高度な技術が求められる難曲ですが、今でも各種演奏会などでよく演奏される名曲です。
<演奏⑮:シエナ・ウインドオーケストラ>⑯『ディスコ・キッド』
『ディスコ・キッド』(東海林修 作曲)は、1977年の吹奏楽コンクール課題曲です。
冒頭からドラムセットの刻みに乗ってピッコロが軽快にメロディを奏でます。
コンクール課題曲であったとは思えないほど楽しくカッコよくて、今では定番のポップス曲として多く演奏されています。
これほどドラムのかっこいい課題曲にはなかなか出会うことができないので、おすすめです。
なお、曲の序盤の「ディスコ!」の掛け声は、以前にTwitterでアンケートを取ったところ、約9割近くの楽団で行っているそうです。カッコよく掛け声を決めたいところです。
<演奏⑯:龍谷大学吹奏楽部(2013年)>かっこいい曲【映画音楽・ミュージカル】
⑰映画「スターウォーズ」より「メイン・タイトル」
『スターウォーズ』の「メイン・タイトル」は、ジョン・ウイリアムズ作品の中でも最も人気のある代表作で、定番中の定番とも言える傑作です。
映画音楽には数多くの有名曲や人気曲があり、「かっこいい曲」をいろいろと探しましたが、やはりこの曲以上にかっこいい曲はなかなかないと思います。
なお、今回ご紹介する演奏は、龍谷大学吹奏楽部によるものです。トランペットがHigh Bbをきれいに当てていて、聴いていて気持ちがいいです。さすが龍谷大学吹奏楽部という演奏です。
<演奏⑰:龍谷大学吹奏楽部(2015年)>⑱『キャンディード序曲』
『キャンディード序曲』は、レナード・バーンスタイン作曲の名曲で、原曲は同名の舞台作品(ミュージカル)のために作曲されたものです。
この曲は、かつてテレビ朝日の「題名のない音楽会」のオープニング曲としても使用されていたので、一般のお客さんにもよく知られていることと思います。
今回ご紹介する動画は、佐渡裕さん指揮のシエナ・ウインド・オーケストラの演奏です。
「序曲」にふさわしく冒頭から金管が鳴り、木管楽器のテンポの速いメロディーが続きます。
中間部に美しいゆったりとしたメロディーを挟んで、一気に駆け抜けるような華やかな曲なので、演奏会の幕を開けるオープニング曲としてもおすすめです。
<演奏⑱:シエナ・ウインド・オーケストラ>かっこいい曲【ジャズ】
今回は、ジャズの中でも「シンフォニック・ジャズ」に分類される曲をご紹介します。
⑲『ラプソディ・イン・ブルー』
『ラプソディ・イン・ブルー』は、原曲は1924年にジョージ・ガーシュウィンによって作曲されたジャズバンドのための曲で、後にオーケストラ曲などに編曲されました。
オーケストラや吹奏楽にピアノがメインで加わり、いわばジャズが融合したピアノ協奏曲のような音楽になっています。
しかし、この曲でかっこいいのは、やはり冒頭のクラリネット・ソロです。低音域のトリルから駆け上がるポルタメントは、クラリネット奏者なら誰しも憧れるソロなのではないでしょうか。
この曲は、『のだめカンタービレ』などの影響もあってか、一般のお客さんにもよく知られている曲なので、コンサートのメインの1曲としてもおすすめします。
<演奏⑲:洗足学園音楽大学ホワイト・タイ ウインド・アンサンブル>かっこいい曲【ロック】
⑳『ディープ・パープル・メドレー』
ディープ・パープルは、イングランド出身の大人気のハードロックバンドで、この曲は、彼らの代表曲の中から、以下の3曲をピックアップしてメドレーにしたものです。
- 『バーン(Burn)』
- 『ハイウェイ・スター(The Highway Star)』
- 『スモーク・オン・ザ・ウォーター(Smoke on the Water)』
今回ご紹介する動画は、東海大学付属高輪台高校吹奏楽部の演奏です。
曲自体もかっこいいのですが、彼らの遊び心あふれる振り付けが、音楽をさらに一段と楽しくカッコいいものにしています。
<演奏⑳:東海大学付属高輪台高校(2017年)>いかがでしたか?

今回ご紹介した「かっこいい曲」の中に、皆さんにとっての「かっこいい曲」はありましたか?
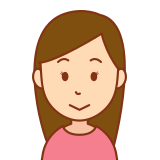
今回は、まっしーの「わがまま企画」にお付き合いいただきありがとうございました!
今回ご紹介しきれなかった「かっこいい曲」が、まだまだ沢山あります。
また機会があれば、ご紹介していきたいと思います。
では、次回の記事でお会いしましょう!






