皆さん、こんにちは。管理人のまっしーです。
新型コロナの影響を受けて演奏活動に制約を受けている吹奏楽部・楽団さんも多いことと思います。
2020年度の吹奏楽コンクールは残念ながら中止となってしまいましたが、今後は定期演奏会や文化祭・学園祭などの各種コンサートに向けて、少しずつ様子を見ながら徐々に練習を再開していく楽団の方も多いのではないでしょうか。
さて、当サイトでは、今回、そんな皆さんを応援するため、コンサートで盛り上がる人気の「吹奏楽ポップス曲」を10曲厳選してご紹介していきたいと思います。
文化祭・学園祭や各種演奏会のポップス・ステージを盛り上げる曲としておすすめです。

ポップス曲で楽しく盛り上がるコンサートにしたいよね
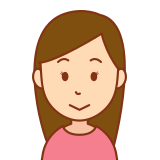
そうね。今回は、厳選した10曲をランキング形式で演奏動画付きでご紹介していきます!
はい。今回、曲の選定とランキング順位付けにあたっては、管理人の周囲の吹奏楽関係者に事前にリサーチを行いました。なお、最終的な判断は管理人が行っていますので、予めご了承ください。
それでは、早速ご紹介します。
第10位『銀河鉄道999』《樽屋雅徳編曲版》
第10位は、樽屋雅徳編曲版の『銀河鉄道999(The Galaxy Express 999)』です。
樽屋雅徳氏といえば、『マードックからの最後の手紙』や『マゼランの未知なる大陸への挑戦』などの作曲家として大人気ですが、その樽屋雅徳氏が意外にも『銀河鉄道999』を編曲されています。
前奏部分から「樽屋ワールド」が存分に感じられるアレンジになっています。
今回ご紹介する演奏は、大阪桐蔭高校吹奏楽部による演奏です。
アップテンポで高校生らしくエネルギッシュな演奏で、とっても魅力的なステージになっています(なお、一部に歌を入れるなど、再アレンジされています)。
<演奏:大阪桐蔭高校吹奏楽部(2019年)>では、続いて第9位に行きましょう!
第9位『ディズニー・メドレーⅢ』
アニメつながりで、ディズニー系メドレーの中からランクイン。第9位は『ディズニー・メドレーⅢ(Disney Medley Ⅲ)』(編曲:真島俊夫)です。
ディズニー系メドレー曲には、いろんな編曲の楽譜がありますが、私がこの曲をおすすめする理由は、編曲者が真島俊夫氏でアレンジがとっても良いからです。真島俊夫氏と聞いてピンとこない方でも、あの『宝島』や『オーメンズ・オブ・ラブ』の吹奏楽版を編曲した方といえば、すぐにその魅力が分かることでしょう。
ソロがアルト・サックス、ユーフォニアム、トランペットにあって、聴かせどころも満載なので、おすすめします。
また、他のディズニー系メドレー曲やジブリ系のメドレー曲をお探しの方は、ぜひこちらの記事↓もご覧ください。
第8位『ディスコ・キッド』
第8位は、『ディスコ・キッド(Disco Kid)』(作曲:東海林修)です。
この曲は1977年の吹奏楽コンクール課題曲で、当時「ドラムセットが登場するポップス課題曲」として注目と人気を集めました。今なお大人気の曲です。
課題曲としてはかなり難度が高くて、当時の全国大会でこの課題曲を演奏して金賞を受賞した中学・高校は1つもなかったそうですが、本当に楽しい曲なのでおすすめです!
演奏は、龍谷大学吹奏楽部です。とっても丁寧で上手な、お手本のような演奏です。
<演奏:龍谷大学吹奏楽部(2013年)>第7位『スウィングしなけりゃ意味がない』
第7位は、 スウィング・ジャズの名曲 『スウィングしなけりゃ意味がない(It don’t mean a thing)』です(New Sounds in Brass)。
まずは、東京佼成ウインドオーケストラの演奏をご覧ください。めっちゃカッコいいです!
東京佼成ウインドオーケストラの演奏
<演奏:東京佼成ウインドオーケストラ>
やっぱりプロの演奏は凄かったね! もし難易度的に難しいようであれば、他の編曲版にする手もあるよね。
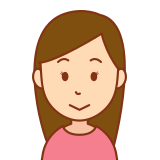
そうね。ところで、まっしー、私、京都橘高校の演奏も見てみたいな。紹介してよー
はい。やはり、この曲を紹介するときは、京都橘高校吹奏楽部(Kyoto Tachibana Senior High School Band)に触れない訳にはいきませんね。「オレンジの悪魔」(Onange Devils)の異名を持つ楽団の皆さんです。
編曲はニューサウンズ・イン・ブラスとは別ものです。ご覧ください。
京都橘高校吹奏楽部の演奏
<京都橘高校吹奏楽部(2014年)>
うわぁ、やっぱり凄かった~! どうしてあんなに飛び跳ねながら演奏ができるんだろう!?
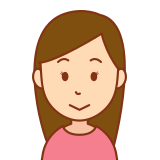
彼女たち、上手いし かわいいわよね~。私にとっては「悪魔」というより「エンジェル」よ♡
第6位『シング・シング・シング』
続いてもう1曲、スウィング・ジャズの名曲をご紹介します。
第6位は、『シング・シング・シング(Sing Sing Sing)』(編曲:岩井直溥 )です(New Sounds in Brass)。
冒頭は力強いドラムと、トロンボーンとトランペットの掛け合いで始まり、続いてサックス群のメロディに移ります。
誰もが一度は聞いたことのある名曲で、これを吹奏楽編成で演奏できるというのは本当に嬉しいことです。
では、東京佼成ウインドオーケストラの演奏をご紹介します。
東京佼成ウインドオーケストラの演奏

ああ、凄かったよね。トランペットのソロやハイトーンがカッコいいし、クラリネットのソロも凄かった!
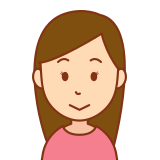
ねえ、まっしー、この曲も京都橘高校のパフォーマンスを紹介してよ~
はい。やはりシング・シング・シングといえば、京都橘高校吹奏楽部(Kyoto Tachibana SHS Band)ですよね。ニュー・サウンズ・イン・ブラスとは異なる編曲ですが、ご紹介します。
京都橘高校吹奏楽部の演奏
<京都橘高校吹奏楽部(2016年)>やはり凄かったですね。見て良し聴いて良しの最高のエンターテインメントだと思います!
それでは、第5位に行きましょう。
第5位『ティコ・ティコ』
第5位は、『ティコ・ティコ(Tico Tico)』(編曲:岩井直溥)です。
やはりラテン系音楽は、ステージが明るく楽しく盛り上がるのでおすすめです。
この曲は、複数の編曲版の楽譜が出版されていますが、ニュー・サウンズ・イン・ブラス版がアレンジも良いのでおすすめします。
演奏は、洗足学園音楽大学ブルー・タイ ウィンド・アンサンブルです。
第4位『エル・クンバンチェロ』
続いて、もう1曲ラテン系音楽をご紹介します。 第4位は、『エル・クンバンチェロ(El Cumbanchero)』(編曲:岩井直溥)です。
この曲がどれほど盛り上がるかは、この動画↓をちょっとご覧いただければお分かりいただけるかと思います。
<演奏:奈良県バンドフェスティヴァル 大学・一般合同バンド>いやぁ、指揮者の方の弾けぶりには驚きましたが、とにかく楽しい演奏でしたね。この曲はステージが盛り上がること間違いないのでおすすめです!
第3位『オーメンズ・オブ・ラブ』
第3位は、『オーメンズ・オブ・ラブ(Omens of Love)』です。
THE SQUARE(現・T-SQUARE)の名曲です。
吹奏楽版の編曲は真島俊夫氏ということで、とても魅力的なアレンジになっています。
吹奏楽ファンであれば誰もがご存じのとおり、親しみやすいメロディとノリの良いリズムが人気の名曲なので、ポップス・ステージにとてもおすすめです。
演奏は洗足学園音楽大学ホワイト・タイ ウィンド・アンサンブル、指揮は真島俊夫氏ご本人という、とても貴重な映像をご紹介します。
第2位『ディープ・パープル・メドレー』
第2位は、『ディープ・パープル・メドレー(Deep Purple Medley)』(編曲:佐橋俊彦)です(ニュー・サウンズ・イン・ブラス)。
ディープ・パープルは、イングランド出身の大人気のハードロックバンドです。
今回ご紹介する『ディープ・パープル・メドレー』は、彼らの代表曲の中から、
- 『バーン(Burn)』
- 『ハイウェイ・スター(The Highway Star)』
- 『スモーク・オン・ザ・ウォーター(Smoke on the Water)』
の3曲をピックアップして、メドレー形式に編曲したものです。
今回ご紹介する動画は、東海大学付属高輪台高校吹奏楽部の演奏によるものです。さすが強豪校だけあって演奏も上手くてカッコいいです。また、遊び心満点の振り付けは見ていてとても楽しいものです。ご覧ください。
<演奏:東海大高輪台高校吹奏楽部(2017年)>第1位『宝島』
1番人気は、やはりこの曲、『宝島(Takarajima)』(編曲:真島俊夫)です。
吹奏楽関係者に事前にリサーチを行った結果、『宝島』の人気はやはりダントツ1位でした。いかにこの曲が多くの吹奏楽ファンから支持されているかが分かります。
『宝島』も、『オーメンズ・オブ・ラブ』と同じくTHE SQUARE(現・T-SQUARE)の名曲で、編曲も同じく、真島俊夫氏によるものです。真島俊夫さんの編曲は、どの曲も本当に素晴らしいのでおすすめです。
今回ご紹介する動画は、大阪桐蔭高校吹奏楽部と東海大学付属高輪台高校吹奏楽部のコラボによる「宝島」です。 ご覧ください。
<演奏:大阪桐蔭高校&東海大高輪台高校(2017年)>いかがでしたか?

いろんなポップス曲が聴けたよね。どれも楽しくてカッコいい曲ばっかりだった!
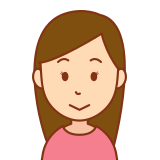
そうね。今回の記事がポップス曲選びの参考になると嬉しいわね。まっしー、またいつかランキング記事やりましょうよ。
はい、機会があれば、また企画したいと思います。
なお、今回のランキングは、事前のリサーチ調査に基づくものですが、最終的な判断は管理人が行っていますので、「この曲がランクインしていない」といった場合はご容赦ください。
では、また次回の記事でお会いしましょう!









